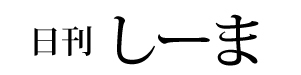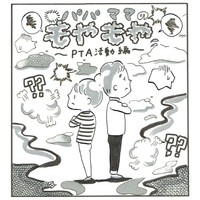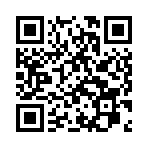女子・子育て 郷土・文化
【女子力】あのハヅキをもう一度!
***********************
時代とともに移り変わる女性のおしゃれ。
奄美市名瀬でいま、ネイルアートやボディジュエリーに注目する女性がいるように、
かつて、なよやかな手を彩る針突(ハヅキ)に胸をときめかせた女性たちが島にいた。
針突とは、奄美群島や沖縄諸島の文化で、女性が手にする刺青のこと。
明治政府が禁止するまで、
針突は島の女性の誇りや憧れであり、ときのファッションでもあり、また、図柄に様々な意味が込められた呪術的なものであるなど大変意味深いものであった。
時代とともに移り変わる女性のおしゃれ。
奄美市名瀬でいま、ネイルアートやボディジュエリーに注目する女性がいるように、
かつて、なよやかな手を彩る針突(ハヅキ)に胸をときめかせた女性たちが島にいた。
針突とは、奄美群島や沖縄諸島の文化で、女性が手にする刺青のこと。
明治政府が禁止するまで、
針突は島の女性の誇りや憧れであり、ときのファッションでもあり、また、図柄に様々な意味が込められた呪術的なものであるなど大変意味深いものであった。
そんな針突に関するみんなのブログをまとめてみましたッ!
写真は奄美を書くさんより
ぐぉおぉ、こ、これがおばあ達の手に!( ゚д゚)

エキゾチックで渋くてかっこいいではないですか!

(有)川畑呉服店 紬レザー かすり さんより
人差し指、中指、薬指にある文様を「矢」または「竹の葉」「柳の葉」などと呼んでいたみたいです。
「竹の葉」は、まっすぐな心。
「柳の葉」は、柔順を意味しているみたいですよ。

の、ように、模様ひとつひとつに意味が込められているのだとか。
筆者もイメージを膨らませる為に描いてみましたッ
 ( ´ ▽ ` )ノ
( ´ ▽ ` )ノ

徳之島柄風
 ( ^ω^ )
( ^ω^ )
奄美本島柄、加計呂麻島柄、請島柄、徳之島柄、
沖永良部島柄、喜界島柄、与論島柄など、地域や島ごとに特徴があるようです。
うーむ。面白い(・Д・)

 現代に蘇る!針突いろいろ!
現代に蘇る!針突いろいろ!
ALOALOのつぶやき さんより
ここて針突グッズが買えますよ
 ( ´ ▽ ` )
( ´ ▽ ` )

型染め工房BIROUさんより
染めもので針突の模様を再現されているようです(^ω^)


などなど、しーまブロガーさんだけでも、針突について書いている方が多く、紹介できなかったブログもあるほどです!
また、ヘナタトゥーやボディジュエリーのようなイメージで針突が現代に復活しても面白いのではないでしょうか。
奄美群島独自の文化が、消えてゆくのを見守るよりも、
こうしたかたちのリバイバルで 確かな島文化に裏打ちされた魅力を活かし、
奄美群島をヘソにして、根強く世界に発信出来ればいーな!
 ( ´ ▽ ` )ノ
( ´ ▽ ` )ノ
じっと手を見つめながらそんなことを考える筆者でありました。。
針突について、OSARIさんが詳しく書いてくれています。
これは必見
 ´д`
´д`  ‼︎面白いです!
‼︎面白いです!(奄美大島 泥染工房 OSARIより転載•編集) では、今回は針突ハヅキの模様について紹介したいと思います。

~模様について~
入墨の文様には各島々とも「施す部分・形状・配置・紋様」など共通点が多くあります。
(もちろん違いも見られます。)
入墨を施す部分においては奄美諸島・沖縄諸島ともほとんど同じです。
文様は「太陽・星等天体に関するもの」「風車・糸巻・鋏・鎌など生活に関するもの」
「魚・蟹・亀(動物)花・葉(植物)」「十文字・渦巻きなどの模様」と多種多用にありました。
手甲部の入墨は総称して「テビラ」と呼ばれ、精巧で華麗な文様から単純な文様・大小さまざまな文様があリ、それぞれに名称と意味があります。
全ては紹介できないのでここでは当Tシャツのベースになった模様について紹介します。
・真ん中の模様は「ゴロマキ」渦巻きで「+」字を形どっている。
(魔除け的な意味の言い伝えがある。)
・拳部の×模様は「アズバン/アゼバン/アジバン」と呼ばれている。交叉の意。
(指掌骨部に多く使われている。)
・指背の模様は総称で「イビバナ(指の節の意)」と呼ばれ、各島でいちじるしい違いがみられる。
(大島本島では人差し指、中指、薬指にある文様を「矢」または「竹の葉「柳の葉」などと呼んでいた。)
Tシャツデザインの指部に使用しているスカイツリーの様な模様は、当工房がある笠利町で多く使われていた模様です。(この模様の名称や意味は紹介がありませんでした。)
・手首部(表)の三角+菱形は「サスカ」と呼ばれている。
(手首には入墨をしない人もいるが、精巧な入墨をする人には施されている。)
・手首部(内)(Tシャツの前の模様)は「鳥の羽・魚の尾・亀の口・鎌・マキ(ゴロマキと同意)」
などを一つにまとめた模様になっている。


~針突ハヅキのその後~
奄美では明治9年に政府から入墨の禁止令が布告されました。
しかし旧来の慣習を直ちに改めることは困難であり、また徹底していなかったこともあり
すぐに廃絶には至りませんでした。
その後、明治15年刑法施行と同時に入墨をした者は処罰されるようになり、また警察の説諭も徹底され次第に矯正されていきました。
それでもひそかにこれを業とする入墨師や施術者もおり、廃絶までには年月がかかったようである。
沖縄では当初施行を見送り、(明治32年)奄美から遅れること二十余年の後に法令により禁止されました。